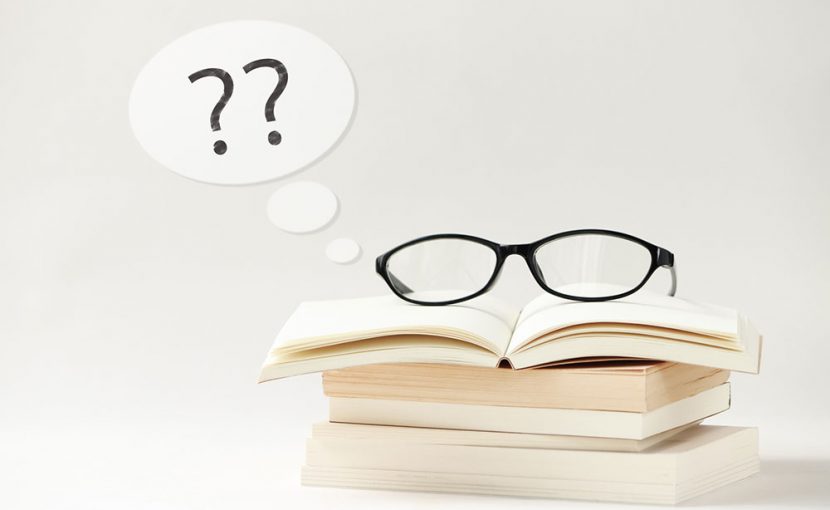高次脳機能障害という言葉を近年よく耳にするようになりました。脳梗塞や脳出血では手足の麻痺や言語障害が起こりますので、周囲からも脳の病気だとすぐ気づかれます。高次機能障害は交通事故やスポーツで脳内に出血や脳挫傷などの器質的損傷を受け、色々な中枢神経症状を残した状態で若い年代に多いのが特徴ですが、目に見える麻痺などはありませんので外来や入院中でも見逃されることがあります。社会復帰したあとも十分に適応できず元の職種に戻れない、人間関係を構築できないなど社会的に取り残されていくという問題を含んでいます。本人にとっても受傷前の自分とは明らかに違うため、もどかしい生活を強いられることになるのです。主な症状を紹介します。
1.注意の障害
私たちが物事を考えて行動するためには、あることに注意を向けそれを一定時間持続させる、つまり注意を継続させる能力が必要です。これが障害されると周囲に起こっている状況を正しく把握できなくなります。業務中にぼんやりする、反応が遅い、反応にむらがある、簡単な指示には従えるが少し複雑な仕事ができないなどの障害が出ます。仕事の能率が極端に悪くなったりミスが多いことを同僚や上司に指摘され仕事を続けにくくなります。主に右半球の前頭葉や側頭葉が障害された時に起こるとされています。
2.記憶の障害
いつどこで何が起きたのか何を言われたのかを思い出せない記銘力障害が生じると社会生活上大きな支障となります。自分のなすべき仕事、指示されたことを忘れるために仕事を遂行できなくなります。外傷性脳損傷では前向性、逆行性ともに記憶が失われますが、外傷時に近い記憶ほど失われ、過去にさかのぼるほど思い出しやすい傾向があります。海馬、視床、前脳基底部などの損傷で起こるといわれています。
3.言語の障害
言語中枢が直接障害された場合におこる読み書きの障害を失語症と呼びます。話せないだけでなく文字を読んで理解したり文字を書く能力が落ちてしまいます。右利きの人の95%以上が左大脳半球に言語中枢がありますので、左半球を損傷された時に失語が起きやすいことが知られています。前頭葉障害では思ったことをしゃべれない運動性失語が、側頭葉、頭頂葉障害では相手の話す言葉、内容を正しく理解できない感覚性失語が起こり日常生活での支障を来たします。
4.遂行機能の障害・社会的行動の障害
退院しても今までの様に社会生活が送れなくなった、仕事ができなくなった、家族とうまくいかなくなったという悩みが生じるのは前頭葉が損傷された場合によく見られる症状です。私たちは仕事や日常生活で何かをしようとする時、その意味を理解し、実行するための段取りを考えます。遂行機能障害の方は言われたことを指示どおりに行なうことは確実にできるのですが、それが終わった後、何をすればいいのかがわかりません。その作業が全体の中のどういう意味を持っているのかがわからないので、ひとつひとつ指示されなければ次の行動ができないのです。知能検査でも正常な事が多いので入院中は気づかれず、社会復帰してから大変悩んで受診する方もおられます。
また、社会的行動障害が目立つ方は、対人関係において相手の気持ちを読み取れなくなり、場にそぐわない発言をしたり、情動を抑えきれず激しく怒ったり、逆に意欲が極端に低下したりします。家族や周囲の方も外傷前と性格が変わったことを大変心配して相談にお見えになります。
高次機能障害支援モデル事業の統計では、原因は外傷性脳損傷76%、脳血管障害17%、低酸素脳症2.8%で外傷が圧倒的に多く、しかも年齢では39歳以下が72%を占めています。
認知症も広い意味では高次機能障害とも言えますが、認知症が高齢者に起こり基本的に治癒が望めない病気であるのに対し、外傷性高次機能障害は若い人に起こりリハビリによる回復が期待でき、社会復帰するという目的がある点が大きく異なります。また原因も交通外傷だけでなく、ボクシングのように頭部外傷をくり返すことで発症する事もあるので社会問題化しているのです。