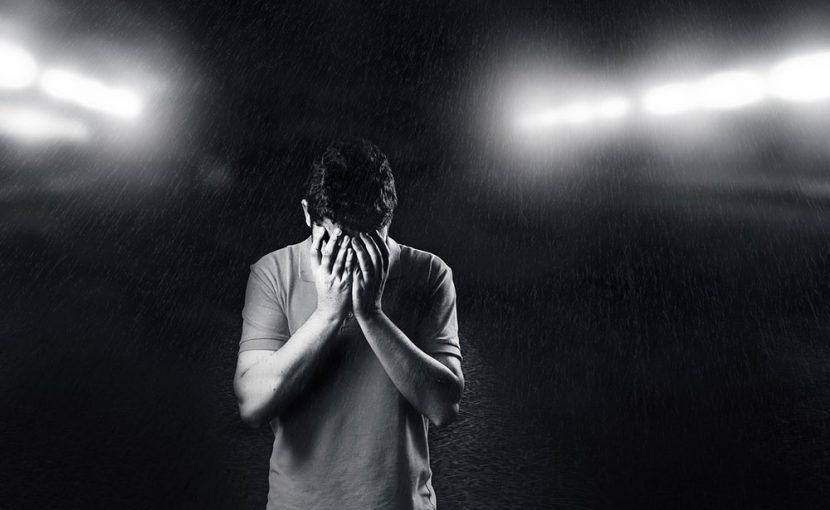高齢者の「老嚥」は栄養障害や誤嚥性肺炎の原因となる大きな問題です。嚥下障害に対する留意点にはどのようなものがあるのでしょうか。
1.口腔機能療法(口腔ケア)
嚥下の第一段階、口腔内の衛生状態がまず非常に重要です。口腔内の食物残留や粘膜乾燥のため、特に高齢者では衛生状態の悪い人が多くみられます。丹念に歯磨きをして口腔内環境を維持することは、虫歯や歯槽膿漏の予防という意味だけでなく、「肺炎や呼吸器感染症の発症率を低下させること」が統計学的に証明されています。
2.食べ物の調整法
多くの施設で嚥下困難の方にはとろみをつけて食べやすくしています。この適度な粘性が食べ物のまとまりを良くし、喉頭(気管)への誤入を防止します。とろみ食は水などの液体に比べると口腔内での保持しやすくなるので、喉頭への流入速度が遅くなり、反射の遅れに対応しやすくなるのです。また、舌触りがはっきりしていて、冷たくて、味の濃い食べ物のほうが誤嚥は起こしやすいと言われています。食べ物の温度調整にも留意すべきです。
3.摂食、嚥下訓練
嚥下訓練は誤嚥を防止するために大変重要です。最もよく行われている方法は「顎引き嚥下」や「頚部回旋、頚部側屈による嚥下」です。むせやすく飲み込みの悪い方はバリウム検査をして嚥下状態を確認します。するとどのような体位で飲みこんだ時に、どの場所に最も食べ物が残りやすいのか、逆にスムーズに入っていきやすいかがわかります。飲み込みやすい方向に頚部を回旋させて食べる訓練をすることでむせる回数が顕著に減り、誤嚥を予防する効果が期待できます。バリウム検査を行えない方では、顎を引いたり、左右に回旋させたりして、どの角度、どの方向で嚥下させると最もむせにくいかを毎回チェックしておくと、周囲の方はアドバイスしやすくなると思います。