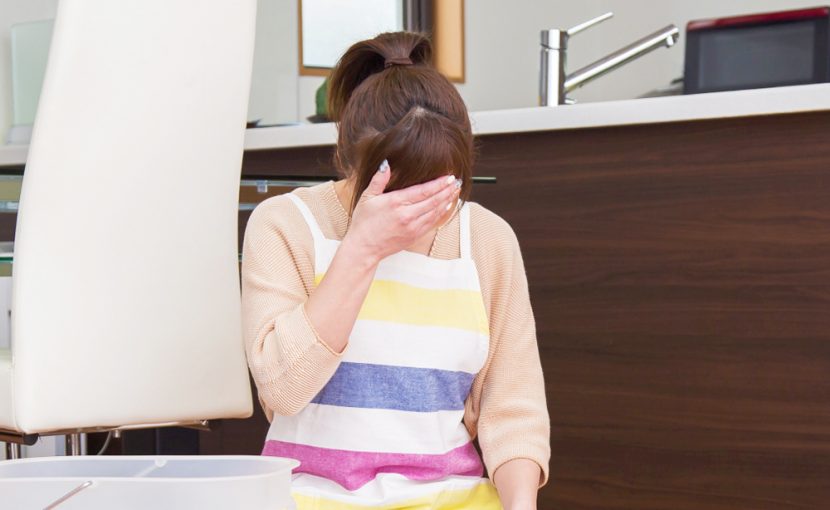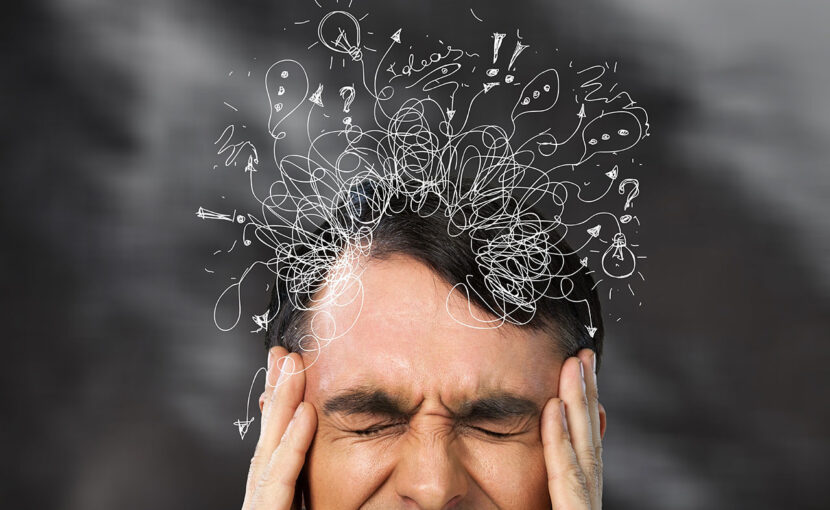まずは症例を見てみましょう
SASと聞くと音楽好きの方ならサザンオールスターズを連想されるかもしれませんが、睡眠時無呼吸症候群もSAS(Sleep Apnea Syndrome)と略して呼ばれます。次のようなケースを見てみましょう。
患者さんは45歳、肥満で高血圧の男性です。数ヶ月前からなんとなく朝から一日中頭がすっきりしない、物覚えが悪くなって仕事のミスが増え部下に指摘される、という切実な訴えで受診されました。診察しましたが神経学的には異常はみられません。うつ病の様に気分が落ち込んでいるわけでもなく、若年性認知症の様に記憶力が極端に低下しているわけでもありません。そこで詳しくお話しを伺いますと、奥様から毎日「いびき」を指摘されること、「日中の眠気」が異常に強いということが分かりました。SAS(睡眠時無呼吸症候群)セルフチェックを行いますと24点満点で18点もあり、この病気が強く疑われたのです。
SASではいびきの性質が問題です
深酒や過労など特別な時にかくいびきではなく、日常的にいびきをかいていて、いびきといびきの間に息が止まってしまう方は要注意です。特にこの「無呼吸」が10秒以上あり、その回数が1時間に5回以上ある方、または7時間に30回以上ある方はSASと診断されます。睡眠専門外来での検査が必要です。肥満の方はいびきをかきやすいので、まずは体重のコントロールが大切です。また扁桃肥大やアデノイドなど耳鼻科的疾患が隠れていないかを調べることも必要です。
どういう症状で気づかれるのでしょうか。
まずは「日中の眠気」です。会議や運転や試験など集中して起きておかなければいけないのにどうしようもない眠気に襲われます。新幹線のオーバーラン事件や居眠り事故などこの病気が原因と思われる事故は多く発生しています。「起床時から頭が重い、頭痛がする」という訴えや「一日中頭がすっきりしない」という訴えも多く見られます。先程の患者さんのように頭がすっきりしない、物覚えが悪い、というのはSASにより集中力が低下して社会生活に支障を来たしている状態と考えられます。そのほか「熟睡感がない」「夜中に何度もトイレに行く」という訴えもこの病気の特徴です。
身体に与える悪影響はあるのでしょうか
無呼吸のため酸欠状態となり、心臓や血管系に多大な負担がかかります。高血圧、心筋梗塞、脳卒中になりやすくなります。もともと、高血圧や肥満の方に多い病気ですので、治療せず放っておくと益々そのリスクは高まっていきます。
また、合併症の予防だけでなく、早期の治療によって眠気、だるさ、頭重感などつらい症状から解放され、仕事の能率を回復させて生活の質を上げることができるのです。
生活上はどのようなことに注意すべきでしょうか
-
睡眠中の体位
寝ている時の体位を自分で制御するのは難しいことです。けれども仰向けで寝ると重力の関係で舌やのどの筋肉が下向きに垂れさがり気道を閉塞します。これがSASの原因なのです。なるべく横向きに寝る習慣をつけるようにしましょう。
-
体重コントロール
SASの発生には生まれつきの顔面や顎の骨格の特徴が影響しますので、肥満でない人にも起こります。しかし肥満は増悪因子ですので、気道周囲に蓄積された脂肪を落とすことは気道閉塞の改善に大きく役立ちます。有酸素運動によるダイエットで10%減量するとSASは25%改善すると言われています。
-
アルコール、喫煙、睡眠薬
アルコール摂取は筋肉を弛緩させるため無呼吸を悪化させます。SASの方は少なくとも就寝前4時間は飲酒を中止すべきです。喫煙は気道粘膜に刺激を与えて粘膜を腫脹させ分泌物を増やすので病状を悪化させます。
有効な治療方法は?
-
CPAP(シーパップ)療法
鼻マスクから空気を送り込み、のどを内側から膨らませて息を吸うときにのどがひしゃげるのを防ぐ方法です。これにより昼間の眠気がとれ、集中力が高まるなど多くのデータで有効性が確立されています。
-
口腔内歯科装具
CPAPに次いで有効な方法です。ボクシングで使うマウスピースのようなもので下顎を前方に数ミリ突き出してかみ合わせるようにする方法です。これによって息の通りが良くなりいびきも軽くなります。
治療法の選択は専門医による検査で決定されます。