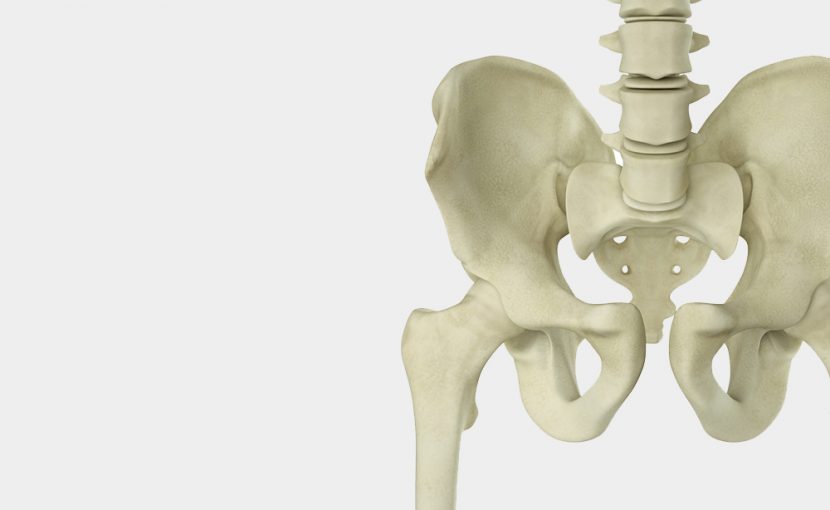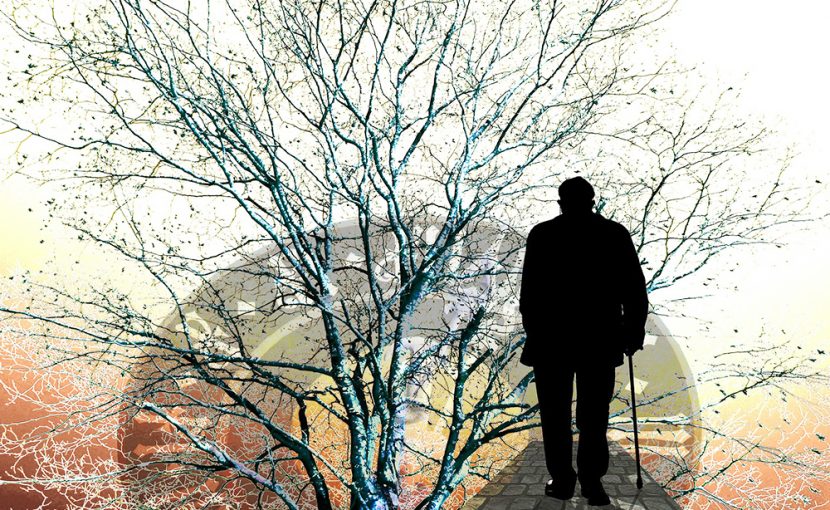不機嫌な認知症患者をみかけると認知症からくる症状だから仕方ない、とつい決めつけてしまいがちですが、実際には身体の不調が原因になっていることもあります。泣いて母親を振り向かせる赤子のように不機嫌になっているのです。水分摂取を気にかけないので脱水傾向になったり、頑固な便秘を抱えている事もあります。そのどちらもが全身状態を悪化させ、認知症特有の不機嫌さに直結しています。認知症施設のスタッフは脱水予防と排便管理、便秘の対策にいつも追われています。
せん妄と脱水
認知機能が急に低下し、会話が通じなくなり、幻覚や妄想、異常行動が出てくるとせん妄状態を疑います。せん妄は寝ぼけが悪化したような意識障害の一つで、認知症や術後の患者さんに良く見られます。このせん妄の重要な原因の一つに脱水が知られています。認知症の方は飲水に対する意識が低くなるので、ケアをする方は適宜飲水の励行と一日水分摂取量を把握することが大切です。水分摂取の少ない人や拒否をする人に対しては無理な促しは反発を招きますので、マジシャンセレクトが有効です。マジシャンセレクトとは選択肢を目の前に2つ提示して「どちらを飲みますか」と選択させる方法です。こうすると人間はついどちらかを選んでしまうのです。
便秘と不機嫌
「三日以上排便を認めない」「または排便があっても残便感があるもの」を日本内科学会は便秘と定義しています。高齢になると便秘になりやすくなります。それは食事飲水量の低下、腹筋群の筋力低下、腸の動きの悪化などが原因です。
認知症患者ではこれに加えて記憶障害や心理行動症状も原因になります。排便した事を忘れて常時便秘を訴える「偽性便秘」や便意を排便のサインと認識できずに我慢してしまいこれが習慣化して便秘になっていくタイプなどです。また「トイレに知らない人がいる」という幻覚妄想からトイレに行かなくなる場合もあります。便秘の訴えに対してはすぐに薬を使うのではなく広い視野で観察する必要があります。
認知症の方はうまく訴える事ができないので、身体症状の不調が不機嫌や易怒性などの精神症状として現われてくることもよくあります。排便状態に関しては周囲がいつも注意を払っておく必要があります。レビー小体型認知症では、レビー小体という異常物質が腸管壁に沈着したり、排便をコントロールする脳幹部に沈着するのでたいへん重症の便秘になることもあります。
便秘は水分摂取や運動不足が原因になりますのでそれらを留意した予防が大切です。食事内容は不溶性食物繊維と水溶様性食物繊維の割合を2対1にすることが推奨されています。けれども介護の現場はそんな理想的な環境ではありませんので、薬物療法を選択せざるを得ないのが現状です。慢性的に便秘薬を飲んでいる人も多いと思いますが、いわゆる「刺激性下剤」という種類に分類されている薬は頻用しない方がいいでしょう。刺激性下剤を慢性的に使うと将来、より難治性の便秘症を引き起こす事が知られているからです。脱水や便秘など認知症とは一見関係なさそうな身体の不調が、精神症状の悪化を引き起こすことに注意が必要です。
参考資料:眞鍋雄太 認知症マネージメント全身疾患の管理他