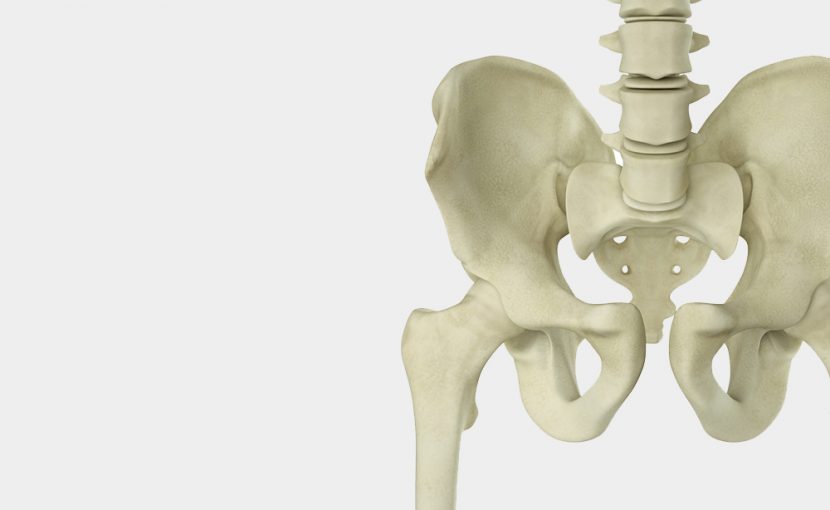高齢化が著しい現在の日本では独居高齢者が増え、医療施設を受診できないケースが増えています。近隣に大きな団地を抱える当院でも独居高齢認知症患者をいかにして受診に結びつけるかが大きな問題となっており、民生委員や包括支援センターの方々と協力しながら日々対応している現状です。病院を受診できない背景には、家族が近くにいないという環境や深刻な経済問題、そして本人の理解力低下による受診拒否があげられます。
受診できない理由
女性の独居高齢者は非常に多く、男性の4倍~5倍と推定されます。独居高齢者女性の多くは様子を見てくれる親族が近くにいないため、病院受診の必要性を誰からも指摘されずに生活しています。生活能力が低下してゆくと、徐々にゴミ処理などの清潔環境を維持できなくなって近くの住民に気づかれるようになるのですが、その時点で多くは認知症に進行しているため「私は何も困っていません。」と援助を拒否し、受診の必要性を認めようとしません。さらにはライフラインを止められ、栄養状態も劣悪となり、緊急保護入院を余儀なくされる事になります。
配偶者と同居の場合でもその配偶者がほとんど年上で生活能力が低下していたり、同時に認知症を発症している事も多く、夫婦間での介護体制が機能していません。男性の高齢認知症では独居は少なく、家族との同居が多くを占めます。そのため女性よりもかかりつけ医が病状を把握しやすいのですが、興奮ぎみの状態、怒りっぽい状態、暴言などの症状で周囲を巻き込んで介護が難しくなっているケースが多くみられます。
対応と今後の課題
配偶者との年齢差や平均寿命の違いから独居高齢認知症者の割合は圧倒的に女性が多くなっています。炊事、掃除、洗濯などは彼女たちが長くやってきた聖域ですので、他人に入られたくないという心理が働き干渉を嫌がる傾向があります。相談員や民生委員と共に現場に足を運んで説得を試みても受診や介護介入を受け入れてもらえません。このような状態に陥っている独居認知症高齢者は都会の中に確実に増えています。声なき声と呼ぶべきかも知れません。
サービスを拒否する単身認知症患者の中にはうつ状態の人が多いというデータもあり、日頃からネットワークを密に構築し、より早い段階でその徴候を評価できるようになれば道筋が見えてくるかもしれません。あくまでも個人には自己決定権がありますのでそれを尊重しつつ最善の対応策を考えることになります。問題解決は容易ではありませんが、医療と行政を巻き込んだ、よりきめ細やかな弱者対策の拡充が必要になっているように感じます。