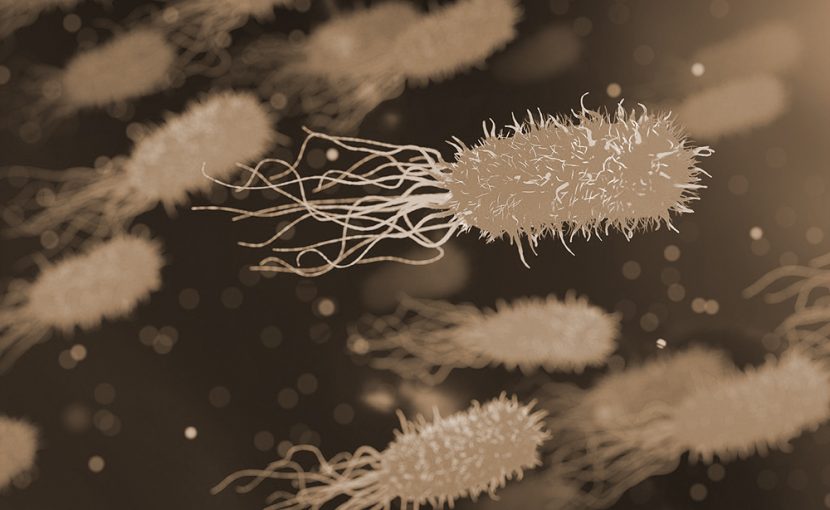2015年10月5日、スウェーデンカロリンスカ研究所はノーベル医学生理学賞を米国ドリュー大学のウィリアム・キャンベル博士と日本の北里大学特別栄誉教授大村智博士に授与しました。「線虫感染症に対する新規治療法の発見」がこの二人の授賞理由です。
20億人の寄生虫感染症
文明国で恐ろしい病気といえば、がん、脳卒中、心筋梗塞などですが、世界全体で最も多くの人を脅かしているのは感染症、中でも熱帯地方の寄生虫感染症です。現在地球上で20億人が発症していると推定されています。大村博士は土壌に生息している微生物がつくる抗生物質を研究するために小さなビニール袋を持ち歩き、行く先々で土を集めてきました。集めてきた土を丸ごと調べるのではどの微生物が何をしているのかわかりません。そこで採取してきた土を微生物がばらばらになるように薄めて、栄養を含む寒天培地で培養します。ばらばらになった微生物一匹一匹はそれぞれが分裂、増殖し、やがて1種類だけの微生物が集まる集団を作ります。そこからその微生物の性質を調べる、という方法です。
ストレプトミセス属「ストレプトミセス・エバミティリス」
1970年代大村教授が注目していた微生物は「ストレプトミセス属」という放線菌の仲間です。結核を治す薬としてストレプトマイシンという薬がよく知られていますが、これもストレプトミセス属の微生物が産生した物質です。大村博士はストレプトミセス属のうち約50種類の細菌に未知の物質を作る能力がある事を発見し、その中の一つが寄生虫治療薬となる細菌だったのです。その細菌はのちに「ストレプトミセス・エバミティリス」と命名されます。この土が静岡県伊東市のゴルフ場近くの土壌から採取されたものであることは広く報道されています。
放線菌が寄生虫の薬をつくる
1970年代大村博士はアメリカの製薬会社MSDと共同研究を行っていました。そこで同時期にMSDで研究を行っていた寄生虫学者キャンベル博士は、大村博士が見つけた放線菌を使い、寄生虫に有効な物質を探し続けました。数々の放線菌の培養液を寄生虫病マウスのエサに混ぜ、寄生虫が減るかどうかを確かめていったのです。その結果「ストレプトミスト・エバミティリス」の培養液に寄生虫を殺す作用があること、そしてその成分は「エバーメクチン」という成分によるものだとわかりました。その後キャンベル博士はエバーメクチンの分子構造を人間用に改良し、特効薬「イベルメクチン」を開発したのです。
フィラリア病とオンコセルカ病
リンパ系フィラリア病は蚊から感染する「バンクロフト糸状虫」などの線虫によって引き起こされ、この成虫は人間のリンパ系に住みつきます。体中のリンパ液の流れが悪くなり全身がむくんで全身が巨大化していきます。これがゾウの皮膚の様に見えるため「象皮病」と呼ばれます。かつては九州にもみられた感染症で西郷隆盛も象皮病だったと言われています。
オンコセルカ病は黒バエから感染する「回旋糸状虫」という線虫がヒトに寄生して起きる感染症です。黒バエに刺されて幼虫が体内に入りますが、成虫になると30㎝から50㎝にもなり、子供である「ミクロフィラリア」を毎日1000匹も生みます。0.3mmの大量のミクロフィラリアが皮膚の下を移動し、眼球に達すると失明します。現在の患者数は2500万人以上と推定されています。
寄生虫病根絶に向けて
イベルメクチンはこれらの寄生虫に極めて有効な薬剤で、1年に1,2回内服するだけで効果があります。MSDが毎年2億5000万人にイベルメクチンを無償配布していることもあり、フィラリア病とオンコセルカ病の新規発症者は激減しています。世界保健機関(WHO)はフィラリア病を2020年までに、オンコセルカ病を2025年までに根絶する目標を立てています。日本での生活では想像もできないような病に苦しむ人たちを救うための目標設定ができたのも、この二人の偉大な科学者の真摯で地道な研究の成果であると改めて敬意を表したいと思います。
参考文献 : 日経サイエンス、ニュートン、熱帯感染症